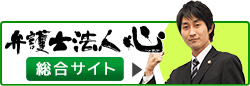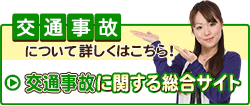1 交通事故で加害者が任意保険に入っていない場合
交通事故で加害者が自動車保険などの任意保険に入っている場合、加害者は保険が保険を使用すれば、保険会社の担当者が加害者に代わって対応や賠償金額の交渉、支払いなどをしてくれます。しかし、加害者が任意保険に入っていない場合には、基本的には自分で被害者対応や賠償金額の交渉、賠償金の支払いなどをしなければなりません。
近年、任意保険に入らずに自動車や自転車を運転して、他人にケガをさせてしまう方が増えています。
被害者自身が、人身傷害補償など自分のケガなども補償される保険に入っていることもありますが、被害者に支払いをした保険会社から求償を求められたり、被害者が加害者に対して直接請求をしたり、訴訟を起こしたりすることもあります。
交通事故のケガの賠償金は高額になりがちであり、保険に入っていない加害者は賠償金の支払いが出来なかったり、一括での賠償金の支払いができないこともあります。
示談交渉や裁判上の和解で、加害者が支払える程度に減額したり、分割を認めた和解をすることもありますが、和解は被害者と加害者の双方が納得しなければ成立しません。
判決の場合には、基本的には一括での賠償金の支払いを命じられることになりますので、個人での支払いができないこともよくあります。
では、訴訟で判決を受けるなどの債務名義を得たにもかかわらず、加害者が賠償金などの支払いをしないときには、どのようにして賠償金の支払いを受ければよいのでしょうか。
2 民事執行手続
裁判で得た権利を強制的に実現させるためには、民事訴訟とは別に民事執行手続を行う必要があります。民事執行手続は、お金を受け取る権利を持った人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を支払う義務がある人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者が強制的に債務者から債権を回収する手続です。民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
交通事故は偶然発生するものですので、あらかじめ担保をとることはできません。交通事故による損害賠償の場合には、財産や給料の差し押さえなどの強制執行手続をすることになります。
3 強制執行手続
強制執行を行うためには、公的に債権者の権利を認めて証明した、判決正本や和解調書正本などの債務名義の正本が必要です。
また、強制執行をする場合には、債権者自身が、債務者のどの財産に対して強制執行をするかを特定して申し立てをしなければなりません。
交通事故の場合には、通常はまったくしらない他人が加害者になりますので、相手がどのような財産を持っているかやどこに勤めているかなどは、加害者本人から情報を得なければ分かりません。
知人とのお金の貸し借りであれば、お金を貸す前などに銀行口座や勤務先などの情報を確認したりあらかじめ担保を取ったりできますが、交通事故の場合はそうはいきません。
もちろん、登記簿を確認して住所の土地や建物の名義人を調べたり、弁護士が弁護士会照会などを使って銀行口座の有無を確認したり、財産開示手続きを行ったりすることはできます。
しかし、不動産を持っていても住所とは限りませんし、裁判後には給料の入金先を変えたり入金後にすぐに銀行口座からお金を引き出していたりすることもあります。
また、そもそも財産がほとんどないこともあります。加害者が生活保護受給者等の場合には、財産の強制執行で預金の差し押さえを行えば加害者の生活ができなくなることもあり、執行自体を控える必要があるかもしれません。
4 弁護士への相談
加害者が任意保険に入っていない場合には、訴訟で判決を得たとしても回収できるとは限りません。訴訟で尋問に出席するなど時間や手間暇をかけても、賠償金をほとんど受け取れないこともあります。
加害者が任意保険に入っておらず自分で支払いを行わなければならない場合には、加害者の支払能力も含めてどのような手続きをどこまで行うか弁護士に相談をし、慎重に検討しなければいけません。